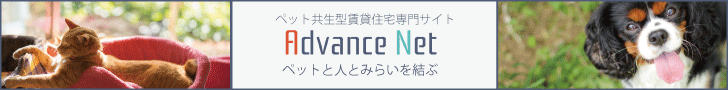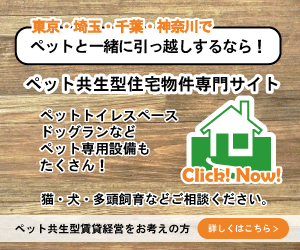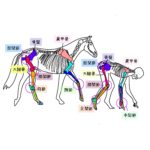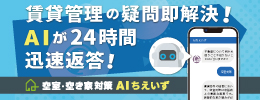今回は、世界中で生きている生き物たちの中で様々な外敵から身を守っている動物たちの紹介をしたいと思います。
これらの動物は、自分達の特性をどのように活かしているのでしょうか?
︎外敵とは?
動物たちが暮らす自然界は実に厳しい環境で、生き残るためには常に外敵から身を守る必要があります。
外敵には、2種類あります。
1つは自分たちを食べる捕食者、そしてもう1つは、毒を持つ生物や直接的に襲ってはこないものの、病原菌を媒介する害虫などです。
このような外敵の存在は、動物たちにとって常に死の危険があるので、逃れて生き延びるための手段が必須となるのです。
︎外敵から身を守る様々な動物たち
〈 オポッサム 〉

オポッサムは南北米大陸に生息する有袋類の仲間です。
120種以上が記録されていますが、なかでもキタオポッサムは米国とカナダで唯一の有袋類とされています。
自分では手に負えない危険に遭遇すると、地面に倒れてよだれを垂らしてぴくりともしなくなります。
つまり死んだふりをするわけですが、それに加えて肛門腺から死臭のようなにおいを発するので、襲いかかった動物はオポッサムへの興味を失ってその場を立ち去るということです。
このような状態を擬死と呼びますが、オポッサムは擬死状態の時も意識を持っているという実験結果も報告されているようです。
〈 ヤマアラシ 〉

ヤマアラシは主にアジアとアフリカに生息しています。
夜行性で、昼間は岩陰や地中に掘った巣穴に潜んでいます。
世界最大のげっ歯目であるヤマアラシのトゲは、身を守るためというよりむしろ攻撃するためのもので、遠くからでも敵に見えるような色になっています。
やってきた敵が脅しても逃げない場合、体の後ろ側にあるトゲで突き刺します。
トゲは敵の捕食動物の体に入り込み、ケガや感染症によって命を落としてしまいます。
またトゲの威力は強力で、内蔵まで到達することもあります。そんな強力すぎる武器を持っているため、ヤマアラシはトゲが不慮の事故で自分にささっても大丈夫なように強力な抗体を持っているそうです。
〈 ヤマネ 〉

ヤマネは、山地帯〜亜高山帯の樹林に生息しています。
樹洞、木の割れ目や地下でも冬眠をし、山の中の人家で見つかることもあるようです。
夜行性で昼間は樹洞などにひそんで生活し、夜間活動して昆虫や植物の実などを食べます。
ヤマネの尻尾の部分の皮膚はゆるく、敵から逃げる時に尻尾を切り離して逃げることができます。
トカゲをはじめとしたは虫類にはよく見られる防衛策ですが、ほ乳類の中でこの逃げ方をする動物はとてもまれです。
しかしトカゲのように尻尾を再生する力はないため、この技が使えるのは一度きりということになるようです。
〈 スカンク 〉

生息地であるアメリカでは、アニメのキャラクターになるほど馴染みの深い動物です。
日当たりの悪い場所を嫌い、日差しの通る森林域や草原、あるいは民家の近くでも生活しているため、人間と出会う機会も少なくありません。
スカンクはおならをして逃げる、というのはすでによく知られていて当たり前だと思う人もいるかもしれませんが、彼らのおならは実際のところしゃれにならない威力をもっています。
筋肉が発達しているため、おならを3メートル先まで放つことが可能で、もし仮に顔面に噴射されてしまったら失明の危険すらもあります。
唯一の弱点としては、おならのチャージに10日間以上かかるので、そうそう何発も放てないという点ですが、彼らを刺激しないに越したことはないでしょう。
〈 カモノハシ 〉

ディズニーキャラクターにも出てくる「カモノハシペリー」でお馴染みのカモノハシ。
カモノハシはオーストラリア東部とタスマニアの淡水域に生息しており、河川や湖、沼地など、水辺の植生が多く、食物が豊富に得られる環境を好みます。
オスのカモノハシは後ろ足に毒腺を持っていて、犬くらいの大きさの動物なら息の根を止めることができます。
つまり人間が刺された場合は死に至ることはないですが、刺されたことのある人は「ものすごく痛かった」と主張します。
興味深いことに、毒を持っているのはオスだけで、メスにはそのような武器は一切ありません。
︎まとめ
今回は、5種類の生き物をご紹介しました。
それぞれの動物たちが自分の特性を活かして懸命に生きています。
時々、「〇〇が〇〇に食べられてしまって可哀想」と思ってしまうこともありましたが、どの生き物も生きていくためにそれぞれが自分の身や仲間のことを考えていることをとても実感させられました。