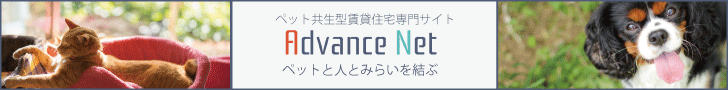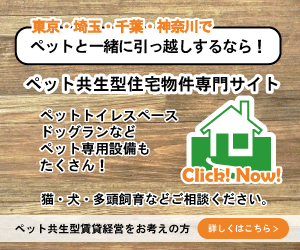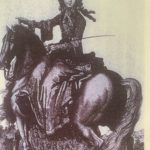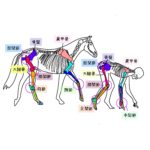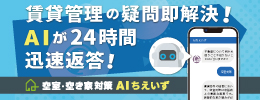乗馬インストラクターがお伝えする馬のお話、今回はナチュラルホースマンシップについてです。
人間は約6000年前から馬を家畜に利用していました。馬を手懐けることを知った人間は、移動手段や農業、戦闘の動力として利用しました。便利な移動手段や機械が発達した現代でも、馬術や競馬、時にセラピストとして馬は人間の傍に居続けています。なぜ、馬はこれほどまでに人に従うのでしょうか?それは馬が進化の過程で備わった性質によるものなのです。
馬本来の性質に根ざした馬の心理を理解した上で馬と接するトレーニング方法は「ナチュラルホースマンシップ」と呼ばれています。

これまでの記事で、馬は集団動物であるという事はご存じいただけたと思います。
野生馬の群れのリーダーは、高齢の牝馬が担っています。雄馬は群れを所有していますが、支配的な高齢の牝馬に従っています。時にリーダーはヨボヨボの高齢牝馬で、群れの大半の馬より体力は劣っていても、鋭い感覚、信頼できる記憶力があり、多くの危機を生き延びた経験から、「いつ、どの方向に、どの速度で走れば良いか」を心得ています。
群れが移動する時、リーダーの牝馬が誘導し、雄馬は後方を走って遅れている馬を急がせる役割を担います。高齢の雄馬がリーダーとなり群れを率いることがないのは、盛りを過ぎると別の若い強い雄馬に座を追われてしまうからです。群れのリーダーは、性別ではなく、経験豊かで確固たる態度を持っていることが条件となります。
つまり、「いつ、どの方向に、どの速度で走れば良いか」を誘導し、「一緒にいて順調で安心だ」と納得させられれば、人が馬のリーダーになれるのです。
馬から信頼されるリーダーになるためには馬のボディランゲージを理解し、リーダーとしての動きをし、馬におてもらう必要があります。
馬のボディランゲージにはたくさんの種類がありますが、その中でも1番基本で小さなボディランゲージである「息」についてご紹介します。
馬は息でさまざまなメッセージを送っています。
 挨拶の息
挨拶の息
遠くから3回息を吐き出します。最後の一息は長く吐き出します。通りがかりの挨拶として匂いを嗅ぎ合うこともあります。馬に近づくときに、見える距離から3回息を吐いてみましょう。
 招き寄せの息
招き寄せの息
歓迎を示す時には柔らかく鼻から息を吸い込みます。
 興味を示す息
興味を示す息
短く吸う息を使って興味を示します。馬に興味を抱いていることを3回の吸い込む息で示すことができます。
 リラックスさせる息
リラックスさせる息
長くてソフトな吐き出す息は馬がお互いにリラックスさせたい時に使います。
 あくび、大きなため息、身震いの息
あくび、大きなため息、身震いの息
馬は感情を解き放つために息を使います。息を強く吐いたり頭を振ったりして吹き飛ばすような感じです。
大きなため息は同意です。
もう一つの解放を目的とした息では短く2回吸ってそれから長く吐く身震いの息があります。緊張と不安を手放すような意味合いです。
 確認の息
確認の息
短く、強い鼻息は恐れにつながっていて、馬は周囲の心配の種になるものに向かって鼻息を吐きます。この息をミラーリング(馬のボディランゲージを真似して返すこと)することで馬を落ち着かせることができます。
 意識的な息
意識的な息
馬が心配しているときは呼吸を最小限にします。心配している馬の周囲で大きな呼吸をするとリラックスさせることができます。馬が一緒に大きなため息をつくまで呼吸を続けます。これは馬との会話の鍵となります。
いかがでしたか?ナチュラルホースマンシップの基本の考え方をご紹介しました。馬の息ぜひ注目して見てみてくださいね。