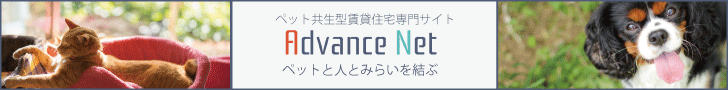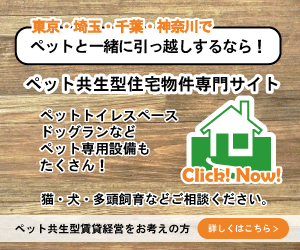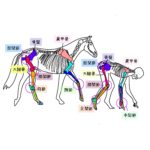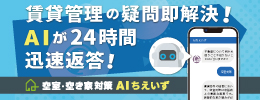日本の梅雨の季節は、5月下旬から7月中旬にかけて続きます。
この時期は湿度が高く、気温も不安定で、日照時間が短くなるため、人間だけでなく猫にとっても身体的・精神的にストレスがかかる環境です。
特に室内で暮らす猫は、外気の変化を直接受けにくい反面、家の中の空気環境や生活リズムに大きく影響されやすいため、飼い主の適切な配慮が不可欠です。
ここでは、梅雨時における猫の健康を守るために飼い主が気をつけるべきポイントについて、具体的にご紹介します。

1. 湿度管理とカビ・ダニ対策
梅雨の代表的な特徴である高湿度は、猫の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。
特に湿度が60%を超えると、カビやダニが繁殖しやすくなり、それに伴って皮膚病やアレルギー症状を引き起こす恐れがあります。
さらに、ダニは猫の耳や被毛の中に入り込んで炎症を起こす「耳ダニ症」や「アレルギー性皮膚炎」の原因にもなります。
こうした問題を予防するためには、室内の湿度を50〜60%に保つことが大切です。
エアコンの除湿機能や除湿器を活用し、日中の換気もこまめに行いましょう。
押し入れやカーテンの裏など、空気がこもりやすい場所も定期的に風を通すよう心がけてください。
また、猫の寝床やブランケット、クッションなどもカビが生えやすい場所です。
これらは週に1回は洗濯し、しっかりと乾燥させるようにしましょう。
カビ臭がする場所には猫を近づけない工夫も必要です。
2. 食欲不振と水分補給の工夫
梅雨時は気圧の変化や気温の上下によって、猫の体調が不安定になりやすく、食欲が落ちる傾向があります。
加えて、気温がそれほど高くない日が続くことで水分摂取量が減り、膀胱炎や尿路結石といった泌尿器系のトラブルのリスクが高まります。
この時期は、ドライフードだけでなくウェットフードやスープを与えて、自然に水分を摂れるように工夫しましょう。
また、給水場所は一か所だけでなく複数に設置し、猫が気分に応じて水を飲みやすい環境を作ってあげることが重要です。
流水を好む猫には、自動給水器の導入もおすすめです。給水器は毎日洗い、水の鮮度を保つようにしてください。
3. 被毛と皮膚のケア
湿度が高いと猫の被毛が乾きにくく、蒸れて皮膚炎を起こしやすくなります。
特に長毛種の猫は、毛玉や抜け毛がたまりやすく、それが原因で皮膚にトラブルを生じることもあります。
また、猫が自分でグルーミングをしても届かない場所があるため、飼い主のサポートが欠かせません。
定期的にブラッシングを行うことで、被毛の通気性を高め、皮膚の清潔を保つことができます。
毛が絡まりやすい脇の下やお腹まわりは特に丁寧にケアしましょう。
ブラッシング時には、皮膚の赤みやかゆみ、フケの有無もチェックし、異常があれば早めに動物病院に相談してください。
また、雨の日に外へ出た場合や換気で濡れた体を放置すると、猫が冷えて体調を崩すこともあります。タオルでやさしく拭き取り、必要に応じてドライヤーで乾かしましょう(音に敏感な猫には無理をしないように注意)。
4. ストレスの軽減
梅雨時は外が暗く、雷や強い雨音が鳴ることが多いため、音に敏感な猫は強いストレスを感じることがあります。
また、日照時間が短いために体内時計が乱れ、運動不足や睡眠の質の低下を招くこともあります。
ストレス対策として、猫が落ち着ける静かな場所を用意することが大切です。
お気に入りの毛布や箱など、猫が安心できるアイテムを置いてあげましょう。
また、飼い主が積極的に遊んであげることで、気分転換と適度な運動ができ、精神的な安定にもつながります。フェロモン製品(フェリウェイなど)を活用することで、不安を和らげる効果も期待できます。
日中はできるだけカーテンを開けて、自然光を取り入れ、猫が窓辺で過ごせる時間を増やすのも良い方法です。
5. トイレの衛生管理
湿度が高い時期は猫のトイレ環境にも変化が起こります。
猫砂が湿気を含みやすくなるため、臭いや雑菌の繁殖が早まり、猫がトイレを嫌がる原因にもなります。その結果、排泄を我慢したり、別の場所で粗相をしてしまったりすることもあります。
トイレは毎日掃除を行い、湿気の少ない場所に設置するよう心がけましょう。
また、トイレ周りにも除湿剤や消臭剤を設置することで、快適な環境を保つことができます。猫砂は吸湿性の高いタイプに変えるのも一つの方法です。
まとめ

梅雨の時期は猫にとって不快で体調を崩しやすい季節です。
しかし、飼い主が日々の生活の中で少しずつ工夫を凝らすことで、猫が快適に、安全に過ごすことができます。
湿度管理、食事と水分の工夫、被毛ケア、ストレス対策、トイレの衛生管理といったポイントを意識し、毎日しっかりと猫の様子を観察することが何よりも大切です。
猫は言葉を話せませんが、小さな変化を敏感に表現します。飼い主がそのサインを見逃さず、丁寧に寄り添うことが、猫との信頼関係を深め、健康を守る第一歩となるのです。