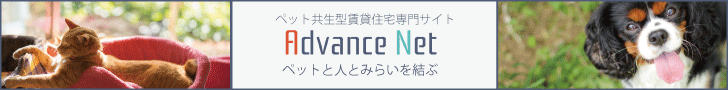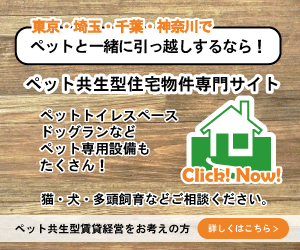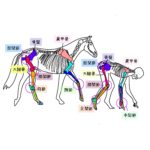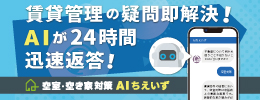はじめに
近年、ペットと暮らす人が非常に多くなっています。2010年、犬・猫だけで21,473,000頭が私たち人間と生活をともにしています。驚くことに、これは6人に1人がペットと生活しているという計算になります。

「あなたにとってペットとはどのような存在ですか」と問いかけると、飼い主様の多くが「子ども」や「兄弟姉妹」など「ペットは家族のような存在」と言われます。家族のように大切な存在ですから、もし失ってしまったら、それはとても大きな衝撃でしょう。
内閣府によって行われた調査では、ペットと暮らさない理由が「世話が大変だから」という回答に次いで、「死んでしまうとかわいそうだから」という「ペットを失う」ことに関することが明らかになっており、それだけ「失う」ということがペットと暮らす際に、大きく影響していることを表しています。
では、「ペットを失う」とはどういうことなのでしょうか。
心や体の反応
ペットとの別れ方は2通りあります。まず、老衰や病気、事故などでペットが死んでしまう場合。ペットの場合、人と異なり安楽死も含まれます。そしてもう1つが、行方不明やご家庭の事情によってペットを手放されるなどの生き別れの場合。例えば、「花火の音に驚いて飛び出してしまい、それ以後見つからない」などです。
ペットを失ったとき、次のような反応が起こると言われています。
- 第1段階:否認
- 例えば、「眠っているだけ」など、「失った」という事実を認められずにいる状態です。
- 第2段階:怒り
- 例えば、「もっと早く気づいてあげれば」などと自分向かう怒りと、「もっと治療をしてくれたら」などと他者に向かう怒りがあります。他者に向かう怒りは、動物病院関係者に向けられやすいようです。
- 第3段階:取引
- 例えば、「この子を生き返らせてくれたら何でもします」など考えてしまう状態です。
- 第4段階:抑うつ
- 怒りもわかず、ただひたすらに悲しい時期です。
- 第5段階:受容
ここに示した反応は一方方向に進むのではなく、各段階を行ったり来たり繰り返しながら、最終的に「受容」へたどり着きます。この段階全てを経ることによって、徐々に頭の中でペットとの関係の整理が行われ、やがて悲しみから穏やかな存在へと受け入れられていきます。
![]()
また、「ペットを失った」とき、大きく分けて「心」と「身体」に反応が起こるといわれています。
- 心の反応
- 悲しみ、罪悪感、空虚感、不快感、失ったペットを思い出す、過去に経験した「死」を思い出す、無意識にペットがいるように振舞ってしまう・探してしまう、など
- 身体の反応
- すぐに涙が出る、眠れない、食欲がわかない、食べ過ぎてしまう、頭重感、頭痛、消化器官の異常、全身倦怠感、やる気が起きない、など

これらの反応はどれも異常なものではなく、大切な存在を失ったとき誰にでも起きる反応です。もちろんペットとの関係は人それぞれですから、みなさんが全く同じ反応をするわけではありません。涙が止まらない方もいれば、どこかぽっかりと穴が開いたように感じる方もいるでしょう。
愛着の強い方やペット一頭と暮らしている方や女性は、「ペットを失った」とき悲しみが強く表れやすいとも言われていますが、人によって違うものですから必ずしも「こうです。」と断定することはできません。また、どのくらいの期間悲しみが続くかも人それぞれで、家族内でも異なります。
悲しみが複雑になるとき
しかし、時にペットを失った悲しみが複雑になってしまう場合があります。その要因は次のようなことがあげられています。
ペットとの別れ方
- 予期することのできなかった場合
- 死に立ち会えなかった
- 自分の不注意による場合
- 安楽死を選択した場合
など
例えば、自分の不注意で外に飛び出して事故にあってしまった場合、「あのとき、自分がドアをきちんと閉めておけば」と自分を責め続けてしまうかもしれません。また、重い病気で苦しみ獣医師からこれ以上の回復は見込めないと言われ、悩んだ結果「これ以上苦しんでほしくないから」と安楽死を選択した場合、「本当はもっと別の方法があったのではないか」など自分を責め続けてしまうかもしれません。
![]()
個人の問題
- 過去の死別経験が多い・少ない
- ストレスに対する対処能力が低い
- 個人のうつのリスクファクターが高い
など

例えば、大人になるまで死別を経験したことがなく、初めての死別経験がペットだった場合、その衝撃はとても大きなものかもしれません。また、ストレスを受けたときうまく発散することができない人は、悲しみを引きずりやすいかもしれません。
![]()
状況因
- ペット失ったことと同時に起こった、その他のストレス
- ペット中心の生活
- 家族や周囲の支えが得られない
など
例えば、ペットを失う前後で、あまり期間があかずにご家族などを亡くされていたりする場合、その衝撃は大きくなってしまうかもしれません。
![]()
二次的ストレッサー
- 「ペットを失う」ことを軽視・否定する社会の風潮
- 周囲の理解度の低さ
- 間違ったフォロー・アドバイス
など

例えば、ペットを家族のように大切にされていた方にとって「たかがペット」という一言は非常に強い悲しみを与えるものですし、友人に自分が大切にしていたペットを失った悲しさをわかってもらえないのは、とても悲しいものです。また、話を聞いてもらいたいだけなのに、色々とアドバイスをされた上、「次飼えばいいじゃない」など言われてしまったら、絶望感さえ抱いてしまうかもしれません。
悲しみが深刻な場合
ペットを失い悲しみにくれても、多くの場合やがて回復していきます。それは、前述した、各段階を経て受容へと至った結果です。しかし、ごく稀に「問題」となるほど悲しみが深刻となってしまう場合もあるようです。
- 社会的不都合が生じるとき
- 例えば、学校や会社に全く行けなくなってしまった場合。専業主婦の方は家事が全くできなくなってしまう場合も含まれます。人が亡くなった場合は社会的に保障された休みがいただけますが、ペットの場合理解してもらえないのが現状です。
- 病的になるとき
- 例えば、重度のうつ状態やアルコール依存などへのつながりが考えられる場合。しかし、ペットを失った悲しみは誰にでもあるものですので、深く悲しんでいるからといって病気と簡単に結びつけてしまうべきではありません。
- 次のペットが飼えないとき
- きっかけさえあればまたペットを飼うことはできるけど様々な要因によって「飼わない」状態と、「飼えない」状況は異なります。例えば、「つらい思いをしたくないからもう飼わない」という考えは、ペットを失った深い悲しみを「受容」できていないことを意味しているといわれています。
- ペットを失った悲しみが全くないとき
- 悲しみの期間や深さは人によって異なりますが、「ペットを失って悲しい」という反応はペットとの間に相互関係があったからこそ起こるものです。ペットを失ったあと、悲しみを全く感じないということは、相互関係の異質さ、さらには動物虐待の可能性も考えられています。しかし、悲しんでいる様子がないように見えても、実際は一人で悲しんでいたり、時には無理やり明るく振舞ったりしたりする場合もあります。
次回は、ペットを失ってしまったときの対処法について解説します。